シンポジウム「ネイチャーポジティブへの挑戦-生物多様性の喪失は誰の問題で誰がどう解くのか」を開催【生物多様性科学研究センター】
2025.04.03 |
京滋エリアの産官学金が連携したシンポジウムを開催
2025年3月14日(金)、龍谷大学 生物多様性科学研究センターは、大宮キャンパス 東黌101教室において「ネイチャーポジティブへの挑戦-生物多様性の喪失は誰の問題で誰がどう解くのか」と題した産官学金連携のシンポジウムを開催しました。
シンポジウムは生物多様性科学研究センター長である山中 裕樹教授(本学先端理工学部)の発表からスタートし、第1部では多彩なゲストによる生物多様性に関する調査や取り組みの報告発表を、第2部では発表者に加え本学の研究メンバーや金融業界のゲストを交えたディスカッションを実施。生物多様性保全のための社会システム構築に向けてできることは何か、さまざまな立場からの知見が集まる会となりました。
なお、当日の司会は同センターの兼任研究員の丸山 敦教授(本学先端理工学部)が担当しました。
【→イベント概要】 【→プレスリリース】
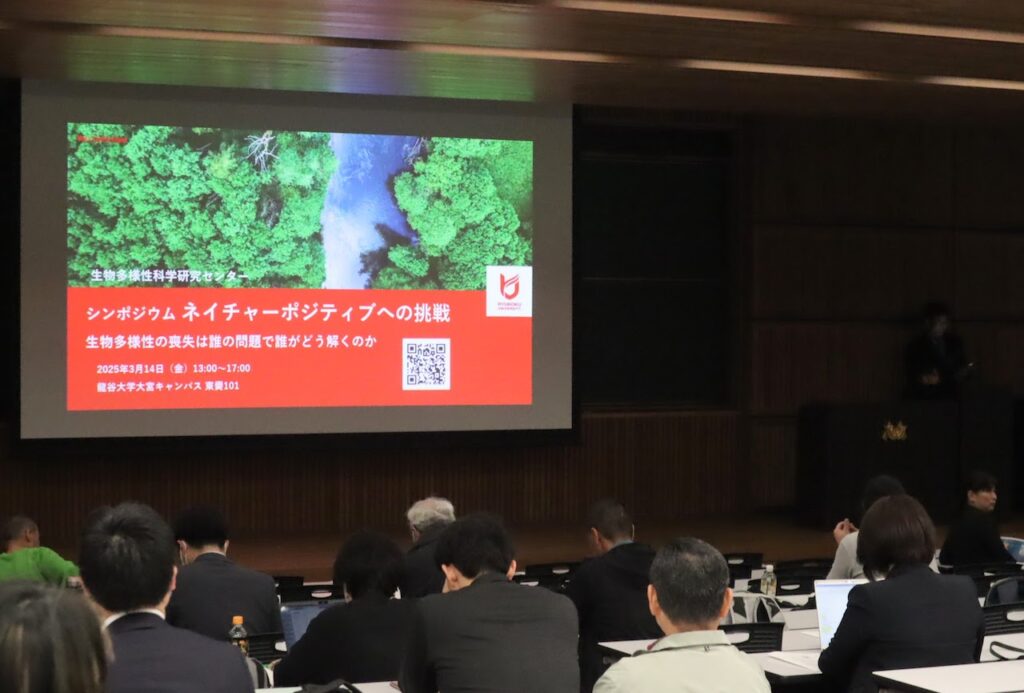

開会の挨拶に立った深尾 昌峰副学長は、2039年の本学創立400周年に向けた「基本構想400」にふれつつ「ネイチャーポジティブや生物多様性保全は本学が掲げる重点テーマ。環境保全を社会のスタンダードにするためにも、ぜひ活発な議論が交わされることを願う」と語り、シンポジウムが幕を開けました。
【第1部:調査・取り組みの報告】
1人目の発表者は山中教授です。山中教授は2021年より地元企業やNPO団体等の協力を得て実施している「びわ湖100地点環境DNA調査」の2024年度の分析結果などを報告。「在来種が増えてきた手応えがある」と語った上で、取得したデータは公開に向けて準備中であると明らかにしました。
またネイチャーポジティブについて、「地域固有の側面が強いことがカーボンニュートラルと異なる難しさだ」と指摘。「取り組みが社会経済システムと絡まり広がっていくには企業の参画が欠かせない」と強調した上で、企業参加の仕組みづくりやそれを促進するためのデータの指標化を議論する場として、生物多様性ステークホルダー会議の設立を進めていることを紹介しました。 「生物多様性科学研究センターは、環境DNA分析を主軸とした環境技術の提供と、課題解決協働体の構築によって、これらの課題解決に貢献したい」と目標を語りました。
2人目の登壇者は、増澤 直氏(株式会社地域環境計画 生物多様性推進上席マネージャー/NPO法人地域自然情報ネットワーク 副理事長)です。
増澤氏は「昆明・モントリオール生物多様性枠組」(※1)や世界経済フォーラムにまつわる資料を提示しながら「ネイチャーポジティブ経営がビジネスチャンスを生む時代に入った」と発言。つづいて日本の生物多様性国家戦略にふれ、ESG投資やTNFDのローカル企業への普及、30by30(※2)などビジネスセクターに求められる重要ポイントを共有しました。
国際的な状況を踏まえて増澤氏は、「企業へのハードルを上げているのが、生物多様性の価値や貢献度を示す指標がない点だ」と指摘し、「自治体には資本投下の根拠となるデータ提示を期待したい」と語りました。また、自然環境を扱う建設コンサルタントの立場から「自然共生サイトを核とするローカルガバナンスの確立をめざすには、企業や自治体、活動団体を円滑に繋ぐ組織が必要である」として、生物多様性ステークホルダー会議への期待が述べられました。
(※注釈)
※1 昆明・モントリオール生物多様性枠組:2022年に採択された生物多様性に関する新たな世界目標。
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/about/treaty/gbf/kmgbf.html
※2 30by30:2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする国際的な環境保全目標。日本では、2023年3月に新たな生物多様性国家戦略「生物多様性国家戦略2023-2030」を閣議決定し、2030年までのネイチャーポジティブ実現に向けた目標の一つとして30by30目標を位置付けている。
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/
3人目の登壇者は、山口 美知子氏(公益財団法人東近江三方よし基金 常務理事兼事務局長)です。
はじめに、地域住民の寄付を基本財源とする東近江三方よし基金の事業支援実績や、地元の信用金庫と共に制度融資を構築した実績などが紹介されました。
つづいて、分野を越えた連携事業が多数展開されている「東近江の森と人をつなぐあかね基金」と、環境省と協働したSIB事業で川の環境改善に取り組んだことなどをピックアップ。特にSIB事業では地域の中小企業の反応が必ずしも良くなかったことから「生物多様性を考えるうえで地域企業の動機づけに課題を感じた」と言及しました。
また山口氏は「社会課題の解決には、既存のお金の仕組みでは難しい局面が多々ある」と述べ、同基金で新たなインパクトファンド(※3)を検討中であることを紹介。「地域の自然資源を最大限生かしつつ、市民のウェルビーイングの実現に貢献したい」と抱負を語りました。
(※注釈)※3 インパクトファンド:財務的なリターンだけでなく、さまざまな社会課題へのインパクト(効果)の実現を重視して運用されるファンド。
4人目の登壇者は、三好 順子氏 (株式会社ダイフク サステナビリティ推進部 環境品質グループ)です。
マテリアルハンドリングシステムを軸とする株式会社ダイフクにおける、環境の取り組みを紹介されました。同社では2011年より環境に関わる全社方針を策定し、2014年には滋賀事業所で生物多様性保全プロジェクトが始動。2050年には同社の商材が環境負荷ゼロで働く世界の実現を目標としているそうです。
三好氏は、自然豊かな滋賀事業所で進む多彩な生物多様性保全活動を紹介し、希少種のヤマトサンショウウオやトンボの保全活動、社外交流の実施、社員の意識向上に向けたシンポジウムの開催などの様子をスクリーンで披露。「当社は、自然資本に与える負の影響をゼロにすることをめざしている」と力強く語りました。
5人目の登壇者は、奥村 浩気氏 (滋賀県琵琶湖環境部 環境政策課企画・環境学習係)です。
「ネイチャーポジティブ×地方創生:自然と共に生きる地域づくり」と題した報告では、行政側の視点から課題と展望が語られました。
奥村氏は「生物多様性しが戦略2024」の取り組みや方針を紹介する中で、「滋賀県は自然豊かで住民の環境意識も高いが、保全に関する取り組みの増加だけでなく質の向上も重要だ」と提言。
びわ湖版SDGsである「マザーレイクゴールズ(MLGs)」の話題に移ると、「ネイチャーポジティブ経営」をテーマに開催された分科会に幅広い職種の人が集ったことを報告。「ネイチャーポジティブは立場の違う人々が集まるキーワードになりつつある。」と実感を込めて語りました。
また生物多様性保全を進める鍵として、的確な情報の取り扱いと人材育成の必要性、中間支援の重要性を説き、「地域ごとの特徴を生かした取り組みが増えるように尽力したい」と展望を述べました。
第1部最後となる6人目の発表者は、今田 舜介氏(滋賀県立琵琶湖博物館 学芸員)です。
今田氏は生物多様性のテーマに関し、「博物館が有する動植物の資料は国家戦略を立てる根拠としても役立つ存在である」と語り、「資料を未来に引き継ぐ博物館のこれまでとこれから」と題して博物館のあるべき姿への考えを発表しました。
報告では「資料は100年後に役立つこともある一方で、一度失われると取り返しが付かない。だからこそ適切に取りためて保管することが大事だ」という点に力を込め、博物館資料が研究に役立った数々の例を紹介。また、資料の収集・保存には常に困難が付きまとうと話し、廃棄リスクを回避するポイントとして、資金はもちろん、組織として持続的な関心を集め続ける必要があると力説。そして、現在の価値のみを根拠としない収集やデジタルデータの利用の促進、知識の社会還元など「より積極的で社会に役立つ姿勢が求められる」と締めくくりました。
【第2部:ディスカッション】
第2部では、第1部の発表者にゲストと本学研究メンバーを交え、2つのテーマでディスカッションを実施。生物多様性データの活用や社会システムの構築に向けた活発な議論が行われ、多様なステークホルダーの協働の重要性が確認されました。
1つめのテーマ「生物多様性調査の価値とそのシステムの確立・維持について」では、山中教授がモデレーターを務め、発表者から3名(増澤氏、今田氏、奥村氏)と、岸本 直之教授(本学先端理工学部)が登壇。
山中教授が多種多様なステークホルダーを巻き込む方法について意見を問うと、増澤氏からは「自然共生サイト認定を受けている企業がもつ環境情報を、自治体や研究機関が有効に循環させる手法が有効ではないか」と意見があり、今田氏は資料保管の観点から「調査の取り組みや採取データの価値を普及するには市民参加型のイベントが有効ではないか」と提案。
岸本教授はMLGsの活動実績から「状況を可視化することが次のステップに繋がると実感している。第三者の客観的評価からアカウンタビリティが果たされることがカギになるだろう」と話しました。
後半、聴講者から「企業のやる気に対し、行政のサポートが不足するケースではどのように働きかけるべきか」と質問も飛びだし、奥村氏は「地方創生や地域課題の解決に繋がる点を伝えてはどうか」、増澤氏は「行政にとって資金面がネックになるのであれば、お金をかけずとも始められることがあると理解を得ることが重要だ」と助言。
山中教授は「行政からの認証が企業にとって大きな意味を持つことは理解できる。私たち科学者が指標決定に関わる際には、正確性だけでなく関わる人々の最大公約数的な納得感も考慮する必要がありそうだ」と述べました。


(本学先端理工学部/生物多様性科学研究センター長)

(株式会社地域環境計画 生物多様性推進上席マネージャー/NPO法人地域自然情報ネットワーク 副理事長)

(滋賀県立琵琶湖博物館 学芸員)

(滋賀県琵琶湖環境部 環境政策課企画・環境学習係)

(本学先端理工学部)
2つめのテーマ「生物多様性データを基軸とした保全のための社会システムの構築に向けて」では、発表者2名(山口氏、三好氏)に、ゲストの山本 卓也氏(滋賀銀行 総合企画部)、只友 景士教授(本学政策学部)が登壇。モデレーターは深尾教授が務めました。
まず只友教授が「地域づくりという長い目で養うべき物事について、合理的経済人の判断だけが正しいとは限らない。生物多様性保全が直面する課題とは、とるべき行動をとれない我々市民の未熟さそのものではないか。市民性の再興が今こそ必要だろう」と問題提議。
すると山本氏が「脱炭素や生物多様性など、大企業は今や取り組まないことがデメリットとなっている一方、中小企業は物価も人件費も上がる中で取り組むメリットが見えていないのではないか。金融機関として企業価値向上に繋げるサポートの必要性を感じている」と発言。それを受けて山口氏が「多様な立場の人が同じテーブルにつく機会を増やすこと。それが共通言語を育み、意識の醸成に繋がるでしょう」と話し、社内の意識向上について尋ねられた三好氏は「たしかに明確な指標がない生物多様性保全は、社内でも理解を深めるのが難しい。しかし環境・社会活動貢献ポイント制度などの動機を与えることで徐々に仲間が増えている実感がある」と独自の試みを紹介しました。
活発な意見交換を受けて、深尾教授は「当センターの生物多様性ステークホルダー会議の構築に向けては、現状の枠組みにはめ込むことなく、小さなトライ&エラーを繰り返していくことが重要だ」と総括。
新たな社会システムの構築をめざす上で、多角的な視点から意見が交わされました。


(本学政策学部/副学長)

(本学政策学部)

(滋賀銀行 総合企画部)

(株式会社ダイフク サステナビリティ推進部 環境品質グループ)

(公益財団法人東近江三方よし基金 常務理事兼事務局長)
シンポジウムも大詰めを迎え、ご協賛いただいた東洋紡株式会社の清水 祐輔氏(総合研究所 環境安全室)が挨拶のために舞台上へ。「各専門家の方々の知見にふれ、知的好奇心が刺激される会でした」とコメントを寄せ、参加者に謝意を示しました。
最後に山中教授が閉会の挨拶に立ち、「生物多様性に無頓着でいることは、どこかの誰かに不自由を強いることと同義である」と力説。そして、ネイチャーポジティブの視点から地域を元気にするきっかけとして、生物多様性ステークホルダー会議の必要性を訴え、「ぜひ多くの方にご参画いただきたい」と会場に呼びかけ、参加者に感謝を述べてシンポジウムは閉会しました。


龍谷大学 生物多様性科学研究センターは、今後もネイチャーポジティブ実現に向けた社会システムの構築に向けて、産官学の多様な立場からの知が融合する機会を設けていきます。